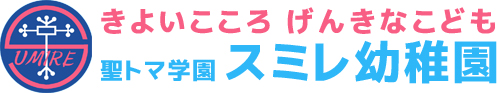幼稚園だより
イエス・キリストは 誕生する場をさがしています
園長 佐藤 直樹
「クリスマスとは何のお祝いでしょうか?」と民放ニュースで特集が組まれ、街頭質問をしていました。その答えとして「サンタクロースの何か…」「全然、考えた事ありませんでした」「キリストの………復活(残念!)」などの答えに微笑ましさを感じました。
先日おこなわれた「クリスマス会」で、年長の子どもたちが演じた『聖劇』の中に、その答えはありました。それは、全ての人の救いのために、神様が神様であるにも関わらず、私たちと同じ人となられたことを祝うのがクリスマスです。マリアとヨセフが泊まるための宿屋を探していたように、私たちの間にもイエス・キリストがお生まれになる場所をつくっていくことが求められています。
日本では本当のクリスマスがあまり認知されていないように、街中のどこを見ても、イエス・キリストの姿を見ることは出来ません。キリスト教幼稚園に通われるのを機に、イエス・キリストがお生まれになる場所(新しい年、ご家庭、皆さまの心)づくりを通して、キリストの平和に満たされた、穏やかな日々となりますように。特に、子どもたちのいる場所が、イエス様がいつも共にいる場でありますように。
貧困の現実に驚いた子どもたちとのクリスマス献金
園長 佐藤 直樹
先日、全学年に「神さまのお話し(宗教)」をした折、「クリスマス献金」の話をしました。その際、ゴミ山に鉄クズ等を拾い集めに来る子どもたちや、地面に落ちたごはんカスを拾い、それで当座の飢えを凌ごうとする子どもの写真を見せると、「えっ、こんな状況の子どもがいるの?」という驚きの表情をしていました。自分自身も数年に渡りフィリピンで生活してきた経緯もあり、ゴミ山の現実や、スラム街の貧困を、子どもたちの姿を通して目の当たりにしてきました。
その日の降園の折に、二人の子どもから「園長先生、私、お手伝いをしてクリスマス献金をするね」と言う「真心献金」の意味をしっかり汲んだ応答をもらいました。
クリスマス献金に参加する上で、あたかも現地にいる、貧困の子どもへの奉仕をするかのように、幼稚園で自分のやるべきことを自分ですることや、家庭でお父さんやお母さんのお手伝いに励むこと。また自分が貧困にある子どもたちに優しく接するかのように、幼稚園のお友だちや、家庭の 兄弟姉妹にやさしく接することなど、子どもの優しい「真心」は、思いやりのある行動や親切を通して現れます。子どもの純粋な「真心」から溢れる、やさしい行動に触れながら、ご家庭皆さんで「クリスマス献金」に参加して戴けると嬉しいです。
子どもの心の成長に感謝をささげる七五三
園長 佐藤 直樹
七五三の由来は諸説あります。その一つは、江戸時代に徳川綱吉が長男「徳松」の健康を祈って始まったと言うものです。文治主義をとった徳川綱吉らしい歳時記の用い方です。また3歳・5歳・7歳を節目とした理由には、暦が中国から伝わった際に奇数は「陽」、縁起がいいものとされており、「3歳で言葉を理解し、5歳で知恵がつき、7歳で乳歯が生え替わる」という成長の節目の歳だとされています。
私たちも子どもたちの成長が感じられるところに、「言葉」・「知恵=物事をわきまえる考えや行動」・「身体の変化」を挙げるかもしれません。幼稚園でも、子どもたちの会話には、様々な語彙(ごい)が年々、増えています。また、お友だちと一緒に遊んでいる中で「これどうぞ…」と分け合う姿は、まさに知恵がわきまえられた証しです。年長さんは「園長先生、歯がグラグラしているんだ」と見せてくれます。
七五三とは「ここまで言葉にも・知恵にも・身体的にも大きく成長しました」への感謝です。
スミレ幼稚園でも11月に『七五三の祝別式』をします。これからも、やさしい言葉使いを心掛ける成長や、思いやりのある行動がとれる知恵、親切を示すことが出来る身体の成長と心の成長を祝別式の中で祈っていきたいと思います。
実りの秋は、「ありがとう」の秋
園長 佐藤 直樹
「お月見」のならわしは奈良時代に伝わり、平安時代になると宮中行事として行われました。江戸時代になると月の鑑賞だけでなく、五穀豊穣を願って月にお供えをする行事となり庶民にも定着しました。お供えは収穫したばかりの里いもです。これにちなんで、十五夜の月は「芋名月」と呼ばれるようにもなります。
新しい年度が始まり半年が過ぎました。子どもたちの成長にも豊かな収穫が、たくさん感じられることと思います。「一緒に遊ぼ!」と誘い合うやさしさ。「入れて」…「いいよ」と仲良くなれる魔法の会話。「〇〇君が教えてくれたんだ」と、やさしくしてくれたお友だちを教えてくれたりもします。
お月見のお供え物が実りへの感謝だったように、スミレ幼稚園でも、10月の実りの秋は「ありがとう」と言う感謝の言葉があふれる月間にできたらと思います。
「ありがとう」って言ってもらえる人生より、たくさん「ありがとう」が言える人生が心を豊かにすると言うのは、本当だと思います。
お話し会テーマ:10月の「神さまのはなし」を通して、親子で共有したいこと。
みんなでする喜びと、協力する心を育てる学期
園長 佐藤 直樹
夏休みはご家庭で、たくさんの思い出に残る日々を過ごされてきたことと思います。子どもたち自身が、ご家族の中でも、様々なことが「出来た!」と言う成功体験や、「これするからね」と言う、自分からの主体的な取り組みに、心身共に一まわりも二まわりもたくましさが感じられたことと思います。それだけに一学期は「自分ですること。自分がすること」というテーマで、その学年や年齢に応じた課題や目標について、自分から取り組み、自分で出来る力を伸ばしていけるように寄り添ってきました。
二学期は「みんなですること。みんながすること」というテーマに取り組みます。夏休みに家庭で育まれた個人の体験や、身についた力を、今度は、お友だちや先生方と作り上げていく共通体験を通して、みんなで共にする喜び…「みんなで出来たね!」「みんなで力を合わせられたね!」と、“協力する”力が深められることによって、みんなを思いやることが出来る心が育つ学期にしたいと思います。