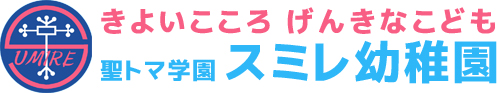幼稚園だより
「七夕の短冊」に込める願いとは、「やり続ける」こと
園長 佐藤 直樹
七夕は日本の大切な年中行事である「五(ご)節句(せっく)」の一つです。五節句とは、季節の節目に邪気を払い、無病息災や豊作などを願うものです。宮中行事だった七夕が、庶民の間に広まったのは江戸時代です。特に寺子屋で学ぶ子どもたちが、習字の上達を願って短冊に願いごとを書くようになったのが始まりだといわれています。色とりどりの短冊に願いごとを込めて笹竹に飾る風習は、織姫さまが機織りの名手だったことから、機織りや裁縫、芸事や書道などの“手習いごとの上達”を願うことが通例となっています。
本来、手習いごとも含め、何事も、もっとうまくなること…つまり習得するには、「反復練習する」ことが何よりです。何度も繰り返し練習する努力が求められます。「天才とは努力する凡才のことである」とアインシュタインは言いました。子どもたちにとっても、得手不得手はあるものです。その時に「ちょっと難しいなぁ」と感じ、心が折れてしまいそうになることがあっても、あきらめずに、もう一度やってみることです。願いごととは、「やり続ける」努力によって叶っていくものです。
6月の雨は「梅」になるか、「黴」になるのか
園長 佐藤 直樹
「梅雨」に「梅」が使われるのはなぜでしょうか? 梅雨と言う漢字は、江戸時代に中国より日本に伝わったとされます。「梅」と「雨」を用いる理由は諸説ありますが、中国の長江下流域で梅の実が熟す初夏の時期と重なったことが梅の字を用いた由来のようです。梅の花が咲く季節は2月から3月にかけてですが、実が大きくなるのは日本も6月頃です。
ところが、元々は違う漢字が使われていたという説もあります。元々は梅の字ではなく、ジメジメとカビが生えやすい季節柄、「黴(かび)」の字を当て「黴(つ)雨(ゆ)」と読んだとも言われます。黴の字が読みづらかったため、「梅」の漢字に変えたとも言われます。
家庭菜園をしていると、梅雨はとてもありがたい時季です。日照時間は短くなるにしろ、野菜の苗にとって、水分を含んだ豊かな土は成長に欠かせない糧です。実を実らせるため、苗にとって梅雨はまさに「梅雨」であり、決して「黴雨」ではありません。
幼稚園での新生活から2ヵ月が経ちました。子どもの成長過程の中で、陰鬱にすら感じられる6月が、実は成長の時季です。腐るかのような「黴雨」ではなく、生活の中で身につくものが、成長の糧としての実になる「梅雨」でありますように。
「粽(ちまき)」の由来を通して、「徳の花」について思う
園長 佐藤直樹
2300年以上前の中国に、屈(くつ)原(げん)という詩人がいました。国王の側近として、正義をもって国を思う彼は、人々から慕われますが、陰謀により失脚し、国を追われてしまいます。その時の思いを綴った「離騒(りそう)」という叙事詩が名作となりますが、国の行く末に失望した屈源は、5月5日、汨(べき)羅(ら)という川に身を投げてしまいます。国民は屈(くつ)原(げん)の死を悲しみ、弔いの供え物を投げ入れますが、屈原に届く前に、川に潜む龍に盗まれていました。そこで人々は、龍の苦手な楝樹(れんじゅ)の葉でもち米を包み、邪気を払う五色の糸で縛り、川へ流したところ、無事に屈(くつ)原(げん)のもとへ届くようになります。これが「粽(ちまき)」の始まりとなり、中国では5月5日に粽(ちまき)を作ることが、災いを除く風習となり、端午の節句と共に粽(ちまき)が日本にも伝わります。粽(ちまき)に結んだ「赤・青・黄・白・黒」の五色の糸は、子どもが無事に育つための「魔よけ」として、鯉のぼりの吹流しの色に反映されていきました。
日本では古来より節句の際に“邪気を祓う”ことが慣例とされましたが、キリスト教の精神では“徳を積む”ことが慣例です。世界中でも五月に「母の日」を祝うように、キリスト教は五月を神の母である「聖母マリアの月」としています。
スミレ幼稚園でも、マリア祭に向けた「徳の花」の実践をします。“やさしい心”を持つために、先ず「〇〇さんに、〇〇の親切をする」と子ども自身が意識して人に“親切”をすること。親切する“思い”をもって“やる”ことが“思いやり”の心を育てていきます。ご家庭に配布される「徳の花」シートに色を塗る意味は、意識するところにこそあります。幼稚園では、「徳の花シール」を貼っていきます。
徳を積む機会を通して、子どもたちの「やさしさ・親切・思いやり」の心が大きく成長しますように。
「心」が育つことを何よりとする幼稚園
園長 佐藤直樹
スミレ幼稚園では、キリスト教精神に沿って「心の教育」、子どもの「心」が育つことを大切にしています。特に素直な「心」そのものが育てば、「学んだことを身につけていくこと」も容易です。
例えば、話しを聞くという場面の時、心が素直な状態であれば、自ずと「きちんと聞こう」とする姿勢の中に素直さが現われているので、言われたことは受けとめられているものです。逆に歪んだ心の状態には、元々、聞こうとする意思は無いので、閉ざされた心には、何も届きません。そこで、何かをきちんと受けとめていこうとする素直な心が育つために大切なのは、普段から子ども自身が「愛されている」と感じられることです。
特にスミレ幼稚園では「やさしい心」・「親切な心」・「思いやりのある心」を大切にしています。やさしい心が育てば、人に対してだけでなく、何かに取り組む姿勢にも自ずとやさしさをもつものです。
親切な心が育つと、丁寧な心掛けが、人にも物事への行動にもにじみ出ます。思いやりの心とは、他者を思いやるだけでなく、自分のやるべきことにも思いや意志を込めて「やっていこう!」とするようにもなるのです。
何かが身につくことを考える際、私たちは、ついつい「理解力」で見極めようとしますが、人の「心」の有り様……「愛されること」が感じられ、「愛すること(やさしさ・親切・思いやり)」を通して、ものごととは身につく視点を、スミレ幼稚園は日々の保育の中で大切にします。
健やかな「心」の成長があるところには…
園長 佐藤直樹
3月の年中行事と言えば「ひな祭り」です。ひな祭りは、季節の節目を祝う「五節句」のひとつで、 正式には「上巳(じょうみ)の節句」と言います。ちょうど桃の花が咲く時期とも重なることから、 「桃の節句」という名で親しまれています。 「ひな祭り」のひなあられは、お米を揚げたポン菓子のことですが、3色(赤・緑・白)と4色(黄が加わる)のものがあり、それぞれ色には意味があります。赤には血を表わす「生命の力」。緑は木々の芽吹きを示す「自然の力」。白は雪をイメージした「みなぎる力」を表すそう です。また、4色ひなあられになると、四季(春・夏・秋・冬)のエネルギーを取り込みながら、1年を通じて健康と幸せを願うと言う意味になります。 ひなあられを節句に食べることで、健やかに育つ願いが込められています。
健やかに育つ上で、心の成長は欠かせません。身体の成長は目に見えて感じられますが、 キリスト教精神に於ける「心」の成長とは、その人がする行いや、取る姿勢が「どのような善い実りを結んだか?」によって見えると言います。特に自分がする行いが、他者に「どのような影響をもたらすのか?」への気づき。つまり、「善い心掛け=行い」の実りを通して、「心」の成長は感じられるのです。だから、「心」が成長しているところには、いつも「やさしさ・親切・思いやり」の心が雰囲気の中にも満ちています。