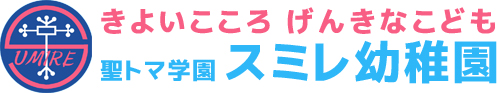幼稚園だより
健やかな「心」の成長があるところには…
園長 佐藤直樹
3月の年中行事と言えば「ひな祭り」です。ひな祭りは、季節の節目を祝う「五節句」のひとつで、 正式には「上巳(じょうみ)の節句」と言います。ちょうど桃の花が咲く時期とも重なることから、 「桃の節句」という名で親しまれています。 「ひな祭り」のひなあられは、お米を揚げたポン菓子のことですが、3色(赤・緑・白)と4色(黄が加わる)のものがあり、それぞれ色には意味があります。赤には血を表わす「生命の力」。緑は木々の芽吹きを示す「自然の力」。白は雪をイメージした「みなぎる力」を表すそう です。また、4色ひなあられになると、四季(春・夏・秋・冬)のエネルギーを取り込みながら、1年を通じて健康と幸せを願うと言う意味になります。 ひなあられを節句に食べることで、健やかに育つ願いが込められています。
健やかに育つ上で、心の成長は欠かせません。身体の成長は目に見えて感じられますが、 キリスト教精神に於ける「心」の成長とは、その人がする行いや、取る姿勢が「どのような善い実りを結んだか?」によって見えると言います。特に自分がする行いが、他者に「どのような影響をもたらすのか?」への気づき。つまり、「善い心掛け=行い」の実りを通して、「心」の成長は感じられるのです。だから、「心」が成長しているところには、いつも「やさしさ・親切・思いやり」の心が雰囲気の中にも満ちています。
「豆まき」の風習に、キリスト教のエッセンスを入れてみる…
園長 佐 藤 直 樹
節分時の「豆まき」は中国から日本に伝わった「追儺(ついな)」と呼ばれる儀式が起源だとされています。古く中国では、病気や災害、飢饉などの厄災は鬼の仕業だと考え、災いを起こす鬼を祓う儀式を行ってきました。これが日本に伝わると、平安時代には、季節の変わり目(=節分)の疫病・災害を鬼に見立て、それを追い払う宮中行事として「追儺(ついな)」を行うようになりました。また豆まきの際の「豆や米=穀物」には魔除けの力があるとされ、お祓いの際に使うようになります。「魔目(まめ)=鬼の目」を投げることで「魔滅(まめ)=魔を滅する」を願う意味で、節分には豆をまいて邪気を祓い、無病息災を願うようになります。
スミレ幼稚園でも子どもたちは、自分自身のエゴなところや、苦手や弱さなどの克服すべき部分を鬼に見立てて「豆まき」をしています。「豆まき」をキリスト教的にとらえる時、鬼を祓うと言う発想よりも、「やさしくなる心や人に親切にする思いやりの心を、イエス様もっと下さい」と、神さまの愛に自分が満たされることを祈り願うと言う、どちらかと言えば「福は内」の発想の方が近いかもしれません。それだけに豆は「まく」よりも、豆をみんなで「分かち合い」、神様のお恵みとして自分の内に「入れる=食する」ニュアンスの方が強調されると思います。
神さまをお迎えすることが新年ということ
園長 佐藤直樹
新年の歳時記と言えば「お正月」です。1月を正月と言うのは、「正」と言う字に年の初め、年を改めるという意味があるからです。一年の始まりである正月は、「年(とし)神様(がみさま)」が各家庭に降臨され、五穀豊穣や家内安全をもたらすとされています。また正月の鏡餅には、年(とし)神様(がみさま)の魂が宿るとされ、宿った鏡餅(=これを年(とし)魂(たま)といいます)を、家長が家族に配ったことがお年玉の由来です。時代が経ちそれがお餅からお金へと変わっていったのです。
年末になると「正月を迎える準備」がありますが、全ては「年神様を迎える準備」であり、大掃除にしても、門松・しめ縄を飾る習慣も、年神様へのおもてなしのためです。全ては神様とのつながりで新年の行事が行われています。
キリスト教では毎年、クリスマス(=主の降誕)の折に、神の子イエス・キリストが私たちのうちにお生まれになることを通して、私たちの日々の歩みの中に、神の恵みと平和を満たしていきます。年長が行う『聖劇』の中でも恵みと平和に満たされた羊飼いは神様に賛美をささげる上で出かけて行きます。また三人の博士たちは、神の子誕生の喜びとして「贈り物(黄金・乳香・没薬)」を奉げます。
年末年始にあたり、神さまをお迎えする意識と共に、新年からの日々の歩みが、神への賛美と感謝を込めた奉げものとして、皆様お一人お一人とご家庭が、神の恵みと平和に満たされた新年となりますように。
神さまへの賛美と感謝のクリスマス
園長 佐藤直樹
12月になると、日本でも盛大にお祝いされているのが「クリスマス」ですね。クリスマスとは英語の造語で「Christ」+「mas(s)」です。意味は「キリストのミサ」となります。キリストとは「油を注がれた者=救い主」の意味で、ミサとは「カトリック教会の礼拝祭儀」のことです。ですから、クリスマスとは「救い主のミサ」となります。日本は「クリスマス」と言う言葉を使っていますが、イタリア語では「Natale(聖夜)」ですし、ドイツ語も「Weihnachten(聖なる夜)」となっており、キリスト誕生の時を示しています。日本で最初のクリスマスを祝ったのは1552年、山口でキリスト教宣教師が日本人信徒と、キリスト降誕祭のミサを行ったことが最初です。
スミレ幼稚園では毎年、年長がイエス・キリスト誕生の次第を「聖劇」として演じてくれています。「聖劇」の中でも、聖母マリアや聖ヨゼフ、また羊飼いが救い主の誕生を祝う上で、祈りとしての賛美と感謝がささげられています。博士たちは礼拝しただけでなく、お祝いの品として黄金・乳香・没薬をイエスにささげています。
日本でクリスマスは、完全に「神さま抜き」のお祝いごととなってしまい、本来の主役である救い主が全く忘れ去られていますが、家族みんなでクリスマスをお祝いするにあたり、「イエス様、いつも私たち家族を守って下さることに感謝します」と「これからもイエス様を賛美する、温かい家庭を育めますように」と言う祈りのフレーズも込められた、賛美と感謝のお祝いに出来ることを願っています。
キリスト教の幼稚園も「七五三」をお祝いしているのは?
園長 佐藤 直樹
11月の歳時記に「七五三」があります。お祝い日は11月15日です。古くは平安時代に宮中で行われた、子どもの年齢に伴った通過儀礼「髪置(かみおき)」「袴(はかま)着(ぎ)」「帯解き(おびとき)」が由来とされ、江戸時代に入ると裕福な町人にも広まり、明治時代には、これらの儀式を総称して「七五三」と呼ぶようになりました。
「髪置(かみおき)」とは、3歳の春を節目に髪を伸ばし始めていくようになること。そして「髪置(かみおき)の儀」にて髪を結い直していました。それが江戸時代になると、男女ともに3歳のお祝いとなりました。
次に「袴(はかま)着(ぎ)」ですが、「袴着の儀」と言う男の子の風習として、5歳になると、初めて袴と小袖を身につけ、手に扇を持つ儀式を行いました。また袴を身につけるとは、子どもから少年になり、男性社会への仲間入りの意味合いをもっていました。
そして「帯解き(おびとき)」とは、7歳前の女の子が付紐の着物をやめ、本式の帯を締めるようになることを祝う儀式です。鎌倉時代からの風習で、江戸時代末期からは、男の子は5歳、女の子は7歳になると行うようになりました。
形としての儀礼を通して、子どもの健やかな成長を年齢の中で喜ぶだけでなく、その子が「神さまから愛されている子ども」として、子どもの成長を支えて下さる神様を思い起こしながら、その神様に賛美と感謝の祈りを皆で奉げることを通して祝う…その意味で、日本のキリスト教界は、日本の風習としての「七五三」を採り入れるようになりました。