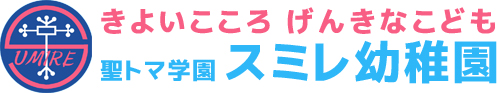幼稚園だより
モンテッソーリだより ~「これ やってみようかな?」~ 2021.5.31
子どもはみんな、すばらしい可能性をもって生まれてきます ・・・その可能性は、適切な時期に、適切な環境を与えてあげることによって、すばらしい発達をみせてくれます。
5月から年少さんも、<ゆりの部屋>でのモンテッソーリ活動が始まりました♪ 新入園の子ども達には、まず『お約束』を伝えます〔室内は歩く・使った物は元に戻す・鈴がなったら止まって話を聞く〕。それから、自分でやりたいことを選びます。みんな、とっても楽しそうです♪ 年中・年長さんは、はじめにモンテッソーリ教具をみんなでやってみます。その後、それぞれ自分で選び、活動します。よく集中している姿に成長を感じます(^^♪
- 野菜切り(ねこの手で)
- ピンクタワー(大きさ)
- はめこみ円柱(ピッタリ!)
- 色水実験(何色になるかな?)
- みんなで 赤い棒(長さ)【年中】
——–モンテッソーリ教育って?————–
今から約100年前、イタリアで女性として初めて医師になったマリア・モンテッソーリは「子どもは自分で伸びていく力をもっている」ことを発見し、それを援助する教育法を確立しました。
自分でやりたいことを選ぶ→ 集中してくり返す→ 満足感→ 自信がつく ・・・ この学びのサイクルが子どもの心を育てます♪ 自分で選ぶことをくり返すうちに、脳の思考回路が育っていくのです。
「自分でできた!」 という満足感や自信を得て、考える力・やりとげる力がつきます。
モンテッソーリ教育では、子どもの発達を助けるために 『教具』と呼ばれる教材を使います。
また子どもが「やりたい」と思う活動のことを『お仕事(しごと)』と呼びます。
①日常生活 ②感覚 ③言語 ④数 ⑤文化 の5つの分野があります(次号より順番に紹介します)
- 3本あみ(紙を編む)
- ぬいさし(紙を縫う)
- 二項式の箱 (a+b)³
- 5本あみ(紙を編む)
- みんなで数のビーズ(1,10,100, 1000)【年長】
★子どもは一人ひとり違います
ゆりの部屋では「やってみたい!」という気持ち(自主性)を大切にしています。子ども達が自分で選んだ活動を自分のペースでやりとげられるように見守っています。 子どもが自分で考えて、自分らしく行動するためには
『急がないこと』と『くり返すこと』がポイントです。 これからも、「ひとりでできた!」という喜びをたくさん経験して、
もっともっと笑顔になってほしいと思います。 そして、親子いっしょに成長を喜び合えますように ♡
モンテッソーリだより ~ 子ども達にたくさんのチャンスを!~ 2021. 2.26
今年度も、ゆりのへやでは 「できた!」の声と輝く瞳があふれていました♪ 子ども達はそれぞれ、やりたいことを自分で選び、手を使って、集中してくり返し、自信をつけてきました。この『学びのサイクル』は、幼児期にとどまらず、一生涯続きます。
小さな頃から『自分の意志で選び決断すること』をくり返すうちに、脳の思考回路がしっかりと育っていきます。どんな状況であっても、子ども達が自分らしく、自信を持って、考え行動できる人に成長するよう、これからもいろいろなことに挑戦していってほしいと願っています♡
- ピンクタワーと茶色の階段のくみあわせ
- 「静かに積まないとくずれちゃう!」
- 折ってかいて切る 🦋
- 文字スタンプ (友達の名前)
- ぐるぐるカード (しりとり)
- あやとり(本を見て、考えて)
- 折り紙 (世界に誇る日本の文化です)
- 「もう一回!」「ひとりでできる!」
- 4本あみ「三角に折って・・」
- 織る紙「どんどんきれいになってくる」
- 幾何図形のひきだし(円・三角形など)
- 100並べ(順序数)
- 連続数字「長くなったかな、後でのばしてみる!」
- はたおり(ステキな色使い♡)
- 数の構成(数のビーズとカードを合わせる)
★子どもは失敗から多くのことを学びます
うまくいかないことや失敗は、大切な経験です。 「そんなこともある」 「また次がんばろう」と思えるような人に育ってほしいですね。 間違えたって大丈夫! 『失敗は成功のもと』だから♪♪
人生の困難に出会った時に、失敗を怖がらず自分でのりこえる力・・・『生きる力』をつけてほしいと願います。そして、心が折れそうな時は、「つらかったね」「いつでも味方だよ」 と伝えてあげてください。
★今年度は、人と一緒にいられる時間の大切さを改めて実感した一年間でした。
毎回、笑顔でゆりのへやに来てくれた子ども達、そして出会いを与えてくださった保護者の皆さまに心から感謝いたします。 いつも、子どもの声に耳と目を向け、子どもの心に寄りそっていかれますように ♡
モンテッソーリだより ~平和をつくるための教育~ 2021.1.29
子どもには、一つのことに夢中になり、同じことをくり返しながら、能力を伸ばす時期があります。
モンテッソーリ教育では、それを『敏(びん)感(かん)期(き)』と呼んでいます。 敏感期には、言葉・秩序・小さなもの・感覚・文字・数・文化など様々なものがあります。 わが子が「今、何の敏感期なのか」をよく観察し、やりたいことを十分にくり返しできる環境を整えてあげることが、子育てのカギです♪
子どもは、求めているものにぴったり合うものに出会うと、何回でもくり返します。 そして、手と五感を使ってくり返すたびに、より集中し、やり終えた後は満足感を得て、顔が変わっていくのがわかります(^^♪
- 野菜切り ・ 色水実験
- ぬいさし(和ばさみも使えます)
- 2本あみでおばけ👻
- 幾何立体「ぴったり!」
- 赤と青の数棒(手を使って数える)
- 折り紙「小さい折紙でも作れる!」
- 十進法「3000!重い!」
- 連続数・・よく考えて、ゆっくり、ていねいに
- 織る紙【年長】 色を選んで、専用の棒に挟んで…集中!
——モンテッソーリの文化教育(コスミック教育)——————————————
◆モンテッソーリは 『世界には平和をつくるための教育が必要』とし、コスミック教育を確立しました。 宇宙に存在する様々なこと(生物・歴史・地理・宗教・音楽など)を伝えていこうとする壮大なスケールの領域です。年長児向(6才から文化の敏感期)
◆地球のすべてのものはつながっていて無駄なものはない→一人ひとりが大切
◆知識を与えることが目的ではなく、「どうして?」という気持ちを大切に、観察したり、手でさわるなどの体験を通して、自分でその先を考えていきます。
◆全体から部分へ進めていきます。(宇宙からスタートします→地球→陸→国…)
- 年長さんに『宇宙・地球』の話をしました。聞く力・考える力・考えたことを言葉にする表現力に驚きました!(地球儀・世界地図などを使います)
———————————————————————————————–
★「待つ」
子どもは自分がやりたいこと・選んだことを尊重され、「できた!」の体験を積み重ねるほど自信がつき、「大切にされている」という自己肯定感を育みます。なるべく指示せずに、子どもが自分で考えて行動できるチャンスをたくさんつくってあげましょう。 あせらせず、子どもの力を信じて 「待つ」ことが大切です♡
でも時には、「次は何をしたらいいかな?」と声をかけて、サポートしてあげるといいですね。
モンテッソーリだより ~ 愛は家庭から ~ 2020. 12. 18
クリスマス会の劇やダンス、すばらしかったですね。 子ども達からたくさんの感動をもらいました♪
練習のつみ重ねの中で、『見る・聞く・考える・待つ』など、大切なことをいっぱい学んだことでしょう。
みんなで協力して一つのことをやり遂げる喜びを知った子ども達。 ゆりの部屋でも、教え合ったり、協力して活動する姿がみられます。 どんな時も、子ども達は輝いています☆彡
- ペグさし「きれいに並べたよ」
- せんたく「自分でできる!」
- みんなで茶色の階段
- ピンクタワー「できた!」
- 待ってる時にフラミンゴ(片足バランス)年少
- 文字うつし「自分でかけるよ」
- ぬいさし「おもしろい!」
- 雑音筒「同じ音をさがすよ」
- 赤と青の数棒「数えられる!」
- フラミンゴで集中「フラフラしないよ」年中
- 数のビーズとカード 「大きい数もわかるよ」
- 「1333‥ちょっと重い」
- 色板〔濃淡〕「よく見るとわかる!」
- ぬいさしブーツ「かわいい♡」
- セガン板Ⅱ(連続数のしくみ)
★ 「愛は家庭から始まります。・・・家族を大切にしてください」 「平和は、ほほえみから始まります」 (マザー・テレサのことばより)
年末の忙しい時期になります。 子どもの目を見て語りかけ、子どもの声に耳を傾けてください。そして、しっかり愛情が伝わるように、「大好き!」と抱きしめてあげましょう。 きっと笑顔になるはずです♪
時には、カードや手紙を書いて伝えてみませんか? 何度でも見られて、うれしい気持ちがふくらみます。 もちろん、字が読めなくてもOKです! おひざにのせて、心をこめて読んであげましょう。
クリスマス、そしてお正月・・・みなさまのご家庭がほほえみにみたされますように、お祈りいたします♡
モンテッソーリだより ~ 数(かず) っておもしろい!~ 2020.11.30
クリスマスの歌声が聞こえてくる中、子ども達は「やりたい!」と思うことを選んで、集中しています。
この時期は、みんなで一つの教具を囲んで一緒に楽しむことができます。順番にお友達がするのを静かによく見ながら待ち、できたら一緒に喜ぶ姿がみられます。お互いを認め合う心が育っているのですね。
「数」は子ども達の日常生活に密着しています。出席シールをはる・ハンカチをたたむ・紙をぬう・編む・折り紙など・・・一つひとつを正確にやってみようとする心(秩序感)がとても大切です。 「どんぐり、数えてみよう」「コップを5つ並べて」・・・手を使って「数」を活用するチャンスがたくさんあるといいですね。
- 幾何立体 「ぴったりのったよ」
- せんたく 「ゴシゴシ♪」
- ピンクタワーと茶色の階段、順番を待って楽しくできます♪
- 魚の名称 「これはマグロ」
- 文字スタンプ(友達の名前)
- 二項式の箱(a+b)3
- 連続数字(ビーズが1ずつ増える)
- ビーズとカードで数作り「大きい数もわかる」
- 100並べ(1~100)
- ハートのバック「教えてあげるね」
モンテッソーリ教育の数教具
- 教具を手でさわり、数え、確かめることによって、理解を深めるように工夫されています
- →教具(具体物)を通して、スムーズに数の概念(抽象)を理解できるようになります
- 感覚教具を十分に使って、感覚の違いがよくわかるようになることが大切です
- 数の土台は生活の中にあります → 秩序のあるものは、すべて数につながっています
教具 - 砂数字板、赤と青の数棒(1~10)、つむ棒箱(0~9)、数あそび、セガン板Ⅰ・Ⅱ(数の構成),100並べ(1~100)、10進法(1,10,100,1000)、連続数字(順番に数を書く)など
- セガン板Ⅰ(11~19の構成) 「10と9で19!」
- 年長さんには、重さが実感できる数のビーズを使って、1から1000の数を紹介します 【10進法の紹介】 先入観をもつ前に、数に出会った子どもは、大きい数への恐れをもちません。
「1のビーズはとても小さい」 → 10 → 100 →「1000のビーズは大きくて重い」・・・順番に手で触って量を体感することによって、確信をもって 「これは1000!」と実感できます。 どんな時も、 『感じる』こと(感覚)って大切ですね♪