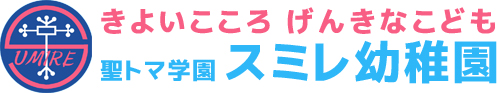幼稚園だより
“心”と“行い”の「二刀流」…
園長 佐藤 直樹
9月といえば中秋の名月(十五夜)ですが、10月は「十三夜(今年は10月15日)」と言う催事があるのをご存知でしょうか。「十三夜」は中秋の名月に並ぶ名月とされており、日本では「十三夜」にもお月見をする 習慣があります。お月見に代表される観月の風習は、中国から9世紀頃(平安時代)に伝わったとされて いますが、10月に行う「十三夜」のお月見は日本独自の風習と言われています。この催事を行う意味は、 十五夜が月の神様に豊作を願うのに対し、十三夜では秋の収穫に感謝しながら美しい月を愛でることです。そして驚くことに、中秋の名月(十五夜)と「十三夜」どちらか一方しか見ないと、「片月見」「片見月」と言われ、縁起が悪いとされているのです。
どちらか一方ではバランスが悪いと言う意味では、人についても、単に「頭が良ければ」とか、「身体さえ丈夫であれば」とは言うものの、知識や力や健康など、人の表に現われるところが、ただ優れているだけでは、やはり片手落ちです。その人の内にある感受性の豊かさ、精神力、心の善良さ・善い心を備えることはもっと大切です。
さて、両方と言えば、「二刀流」で名を馳せる大谷翔平選手を、皆が「スゴい」と言うのは、単に投打の技術力の高さが評価されるだけでなく、彼の心の善良さ、優れた精神の現われとしての仕草やマナー、その行動力や言葉遣いから来る人柄にも「スゴさ」が感じられるからです。
子どもたちにも、「心(思いやり)」の良さが、良い「行い(=やさしさ・親切)」を通して表れるような、心と行いに優れた「二刀流」として成長することを願っています。
「五色の短冊」に込める願いは、キリスト教精神とも同じ
園長 佐藤 直樹
七夕は、日本古来の年中行事である「棚機(たなばた)」と、中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん)」が由来とされています。棚機(たなばた)は稲の開花時期に合わせた禊(みそぎ)の行事、穢れ(けがれ)を清めるための行事でした。そこに機織りや裁縫の上達を祈る中国の行事「乞巧奠(きこうでん)」が奈良時代の日本に伝わり、棚機(たなばた)と 融合し、「七夕(しちせき)」と呼ばれた宮中行事となります。七夕(しちせき)は詩歌・裁縫の上達を願って星に祈り、五色の糸や金銀の針、山海の幸を供える行事でした。そして室町時代になり、宮中行事だった七夕や織姫と彦星の物語が民間に伝わったことで、古来より広く行われていた棚機に ちなみ、「七夕(たなばた)」と読むようになっていきます。
さて、七夕飾りに欠かせない「五色の短冊」のもとは「五色の糸」です。これは陰陽道の自然を表す五行説から来ていますが、❶.青(緑)➡仁:徳を積む・人間力を高める。❷.赤➡礼:父母や祖先への感謝の気持ち。❸.黄➡信:信頼、知人・友人を大切にする。❹.白➡義:義務や決まり事を守る心。❺.紫➡智:学業の向上を意味しています。七夕の短冊への願いごとはこの内容に沿って書くとよいそうです。よくよく考えると、「五色の短冊」に込める願いは、子どもにとって幼稚園生活を過ごすための心と行動の徳育につながるものばかりです。
子どもたちの懸命さにこそ尊さがあります
園長 佐藤 直樹
昔々、北京に掃(そう)晴娘(せいじょう)という手先が器用な少女がいました。当時の北京は連日続いた大雨に人々は悩まされており、彼女は雨が止むよう祈ります。すると「お前が雨の神である東海龍王の妃となる
なら雨を止めるが、ならないのであれば私はこのまま北京を水没させる」と言う声が響きました。晴娘(せいじょう)は北京を水害から守る上でこの言葉を受け入れると、翌日、雨は止み、北京はすっかり晴れ
渡りますが、晴娘(せいじょう)はその姿を消します。自らを犠牲に人々を助けた掃(そう)晴娘(せいじょう)を偲び、中国では雨が続くと、掃晴娘を象った人形を門に吊るして晴天を願う風習へとなりました。この風習が平安時代に日本に伝わり、日本風に変化したのが「てるてる坊主」のはじまりといわれています。
梅雨入りの頃とは言え、運動会当日は、よい日和となることを切に願って止みません。
それと言うのも、連日、運動会練習に励む子どもたちが「お父さん・お母さんに見せるんだ!」とする気概には、水害から人々を救うために自らを差し出した掃晴娘のように、自分自身の成長のためにやることよりも、見てくれているご家族、見守ってくれている神様に自分自身をお奉げしているかのようです。良き日和を得る身代わりとしての「てるてる坊主」にすがらなくても、子どもたちの懸命さは、良き日和を得るに十分足るものです。そのひたむきさには、それほどの尊さがあるのです。
「端午の節句」から「徳の花」について思う
園長 佐藤 直樹
「端午の節句」は、中国から日本に伝来した風習が元になっています。年に五回ある節句(五節句)には邪気が近づきやすいとされ、邪気を祓う上で、神様に無病息災を祈念し、お供えをしていました。「端午」とは、「初めの午(うま)の日」の意味で、「節句」は季節の変わり目のことです。午(うま)は、五(ご)とも読めることから、5月5日が「端午の節句」として、奈良時代以降に定着しました。そして、1948年に5月5日を「こどもの日」と定めたことで、男女問わず子どもたちの幸福を願い、親への感謝を込めた祝日としました。
日本では古来より節句の際に“邪気を祓う”ことを慣例としたならば、キリスト教の世界では逆に“徳を積む”ことの方を慣例としてきました。また世界中で五月に「母の日」をお祝いするように、キリスト教は五月を「聖母マリアの月」としています。
スミレ幼稚園でも、マリア祭に向けて「徳の花」の実践を毎年、行っています。日頃から“やさしい心”を持つ徳や、人に“親切”をする徳、いつも“思いやり”をもって関わる徳を生活の中に習慣化していく上で、徳が積めたことを、子ども自身がはっきり意識することが大切です。ご家庭に配布される「徳の花」のシートに色を塗る意味は、そこにあります。幼稚園では、「徳の花シール」を貼っていきます。徳を積むこの機会に、子どもたちの心がますます健やかに育っていくこと(=「端午の節句」を祝う目的)を願いながら……
「心」を育てることが何よりのこと!
園長 佐藤 直樹
私事で恐縮ですが、スミレ幼稚園の園長になって早や五年目の年度に入りました。スミレに来た当初は、新型コロナウィルス第一波の真っ盛りで、二か月の休園措置を採ったところから始まりその年に生まれた子どもたちが、今年度に新年少として、スミレ幼稚園に入園すると言う経過を振り返った際には、しみじみとさせられるものがあります。
四年の歳月を経た中で、幼稚園で過ごす三年間に、「子どもの成長」に欠かせないと実感していることがあります。それは、子どもが身につけていく「能力」や「技術」を習得することも、様々な「力」を付けていくことも、そして「生活習慣や人間関係」を会得すること等、全ては「心」が育っているかどうかが肝要です。つまり「心掛け」「心持ち」「心の在り様」「心の状態」が良くなければ、身につくものも身につかないケースが多々です。例えば、「我がままな状態とは、自分だけに凝り固まっているので、心が開かれていない分、実際に耳でも聞いていない」ので、良い話・正しい言い分も効き目はゼロです。大人である私たちも、どんな心でいる時に、どんな聞き方をしているかは一目瞭然ですね。それだけに、良い心の状態として、「やさしい心」・「親切な心」・「思いやりのある心」でいられる子どもの姿勢が、聞く耳のあるなしも含め、物事への取り組み方や成長の度合いにも繋がっていくと思います。
それだけに、スミレ幼稚園はキリスト教を通して「心の教育」をこそ大切にするのです。