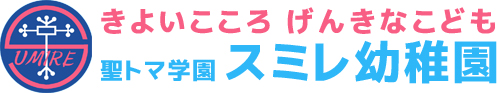幼稚園だより
みんなでする喜びと、協力する心を育てる学期
園長 佐藤 直樹
夏休みはご家庭で、たくさんの思い出に残る日々を過ごされてきたことと思います。子どもたち自身が、ご家族の中でも、様々なことが「出来た!」と言う成功体験や、「これするからね」と言う、自分からの主体的な取り組みに、心身共に一まわりも二まわりもたくましさが感じられたことと思います。それだけに一学期は「自分ですること。自分がすること」というテーマで、その学年や年齢に応じた課題や目標について、自分から取り組み、自分で出来る力を伸ばしていけるように寄り添ってきました。
二学期は「みんなですること。みんながすること」というテーマに取り組みます。夏休みに家庭で育まれた個人の体験や、身についた力を、今度は、お友だちや先生方と作り上げていく共通体験を通して、みんなで共にする喜び…「みんなで出来たね!」「みんなで力を合わせられたね!」と、“協力する”力が深められることによって、みんなを思いやることが出来る心が育つ学期にしたいと思います。
ひまわり組クラスだより 2025.7.17
真夏日が続いていますね。「ヤッホッホ夏休み~♪」と楽しそうに歌う子どもたち。熱中症対策をしながら元気に遊んでいます。「カレー早く食べたいな!」とデイキャンプに向けて期待を膨らませながら過ごしました。あっという間に一学期も終わりを迎えます。運動会や参観で保護者の皆様に頑張る姿を見てもらえた事が子どもたちの自信に繋がったように感じます。一つの事を皆でやり遂げる楽しさを味わいながら、勇気をもって挑戦する姿、練習を重ね少しずつ自信を持って取り組む姿から大きな成長を感じた一学期でしたね。
行事を通して友だちとの仲もぐっと深まり、特にデイキャンプの準備では、グループ名を決めたり、リーダーを決めたりと、自分たちで考えて進める場面が沢山ありました。
「こうしてみよう!」「いいね!」と意見を出し合いながら決めていく事の楽しさや難しさも感じていたようです。友だちとの関わりの中で沢山の刺激を受け、様々な気づきや挑戦を重ねながら、充実した日々を送ることができたと思います☆これからも子どもたちができたことを褒め、その中での頑張りや気持ちの変化にも目を向けながら一人ひとりの「やってみよう」という気持ちを大切に見守っていきたいです!
~一学期毎日の送迎、幼稚園の活動にご理解とご協力ありがとうございました。長い夏休み、病気や怪我無く楽しく過ごせますようにお祈りしています~
- 水遊び
- 放送局🎤クイズを出します!
- いちがっきよくがんばりました! たのしいなつやすみをすごしてくださいね🌻
ばら組クラスだより 2025.7.17
毎日暑い日が続いています。緑の芝に久しぶりに行ってあそんだ日、もう暑くて暑くてたまりませんでした(;’∀’)(笑)「そうだった!ここ、あついんだった」「なつかしいね」など言いながら、体操の時に伊藤先生に教えてもらった、ちょっと頭を使う「だるまさんころんだ」をして元気いっぱい楽しくあそびました。水あそびも、何回か入ることができて良かったです。「もうおしまいよ~」と言っても誰もあがろうとしない様子に、先生達はいつも笑ってしまいます。
進級してすぐに組立体操の練習が始まり、自分のことで精一杯だった年中の時に比べて、友だちを気にして取り組む姿がたくさんありました。行事を通して、みんなで頑張る経験がたくさんできたと思います。この経験が自分だけでなく、友だちと一緒という意識につながり、集団の中での個々の取り組みにも大きな力になりますように…。子ども達はどんな成長を見せてくれるのか?これからとても楽しみです!
そして…デイキャンプです。ダンスがとても上手!みんないつも笑顔で踊っていますね。
ゲームで使う物や看板、名札と準備もリーダーさん中心にグループで協力して活動してきました。お天気がいいと良いのですが…参観で見ていただいたダンス、お家の方とぜひ踊りたいですね。
1学期、子ども達を励まし応援し、支えてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。2学期もよろしくお願いします。
🍉 長い夏休み、身体に気を付けてお過ごしください。🍉
- おちゃごっこ
- じゃがいも収穫
- 保育参観
うめ組クラスだより 2025.7.17
あっという間に過ぎた1学期。4月は保育室に静かに入っていた子どもたちが、運動会を 終えた頃にはぐんとたくましくなり、今では 元気いっぱいに「おはよう!」と大きな声で 挨拶してくれるようになりました。そんな 小さな日々の変化のひとつひとつに、子どもたちの大きな成長を感じます。
先生のことをよく見ていて、物を落としたりぶつけたりすると必ず「大丈夫?」と声をかけてくれます。その優しさにいつも心が温かくなります。「〇〇かえたの?」と気付いてくれることもあって、その観察力に驚かされることもあります。『よく分かったね』と言うと得意げに「だって色が違うから」なんて 返してくれることも。つい『〇〇しないよ』と言ったしまった時に、それを聞いた子どもが友だちに同じことを言っている姿を見て、気付かされることもありました。 “してほしくないこと”を伝えるのではなく、“してほしいこと”を伝えなければと感じた瞬間でした。例えば「走らない」ではなく、「歩こうね」と言い換えることで、子どもたちもより理解しやすく、前向きな行動へと促すことができます。子どもは大人を手本としています。いつも思いやりや優しさを大切に、丁寧さを忘れずに過ごしていけたらと思います。毎日が学びの連続で子ども達と一緒に成長していけることに感謝しています。
長い休みになりますが、夏ならではの経験を通し、新たな発見や学びを重ね、楽しい夏休みにしましょう。暑さで体力が奪われる時期ですので、休息も充分にとってお過ごしください。笑顔で2学期が迎えられますように…
☆1学期ありがとうございました☆
- 水遊び沢山出来ました!着替えが早くなりました♪
さくら組クラスだより 2025.7.17
毎日厳しい暑さが続く中でも、子ども達は様々な活動に取り組み、元気いっぱい過ごしています!
水遊びでも、水の気持ちよさや感触を味わい、元気いっぱい楽しむ姿が見られました♪
あっという間の1学期!特に運動会を終えた頃から心も体もぐんと成長したように思います。みんなで力を合わせて頑張ることを経験出来たのも大きかったようです。個から友だちとの関わりを楽しむようになり、「一緒に遊ぼう!」「大丈夫?」「ありがとう」とう」といった言葉が自然と聞こえてきて、やりとりを楽しみながら一緒に遊ぶ姿が増えました。相手の話に耳を傾けたり、友だちに「すごいね!」と伝えていたり、共に喜び合いながら、思いやりの気持ちが育ってきている姿に心が温かくなります。日々の関わりの中で心の成長も感じ、私たちも子ども達を通して沢山の気付きや学びがありました。一緒に楽しく過ごせたことに感謝しています☆そして、これからも子ども達同士がお互いに刺激しあいながらどのように成長していくのか楽しみです。
4月は自分のことで精一杯だったのが「やってみよう!」と挑戦する気持ちが芽生え、色々なことに前向きに取り組む姿も増えてきました。お当番さんの日は「バッチつけてください!」と張り切り、先生の手伝いも沢山してくれています。「頼りにされている」と思うことで自信にも繋がります。ご家庭でも何か役割を与え、出来た喜びを感じられるといいですね☆
明日からの夏休み、身体に気を付けて、お過ごしください☆子ども達が大好きな歌、ヤッホッホ夏休みの「9月になったらまたあそぼ~♪」の歌詞のように、笑顔で2学期を迎えましょう!
☆~1学期ありがとうございました!~☆
- はじき絵