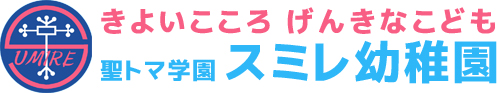幼稚園だより
さくら組クラスだより 2022.6.30
【7月のねらい】・友だちに親しみを持って関わる。
【主な活動】・はじき絵(絵の具) ・水遊び ・お祭りあそび
天気や自然の移り変わりに、季節の変化を感じながら過ごしています。6月になり、さくら組に新しいお友達が入って27人になりました!実習生も入り、新たな出会いに子ども達はとても嬉しそうです。
先日の運動会では、小雨降る中、沢山のあたたかい拍手をありがとうございました。雨でパラバルーンが重くなってしまうので、急遽、競技の順番を変更しました。いつもの練習とは移動の仕方などが変わってしまいましたが、急な変更にも動じず最後まで一生懸命な姿を見せてくれた子ども達、とても立派でした!進級して約二か月での運動会…当日の朝は、緊張した表情で来る子が多かったですが、どの子も大勢のお客様の前で力を発揮しようと頑張っている姿にとても成長を感じました。運動会を終えて「たのしかった!」という子ども達の声と笑顔を見ることができて、先生も嬉しかったです♡そして後日、運動会の思い出画を描きました。みんなで頑張ったパラバルーン、一生懸命走ったかけっこ、どうやったら勝てるか秘密の作戦会議をした玉入れ…(笑)どの絵もいきいきしていて楽しかった様子が伝わってきました。みんなよく頑張りました!!💮
夏の暑さを感じる日が増えてきて、園でも熱中症などに気を付けながら過ごしています。ご家庭でも体調管理をお願いします☆
- 色んな切り紙で人形劇♪「さくらんぼから生まれた亀太郎」のお話に笑ってしまいました(笑)
- 壁面製作「かえる」
- 待ちに待った水遊び💦子ども達も先生もずぶ濡れです(笑)
たんぽぽ組クラスだより 2022.6.30
【7月のねらい】保育者や友だちと一緒に水、砂、泥に触れ、遊ぶ心地よさを味わう。
【主な活動】・水遊び ・お祭りあそび
アジサイの花が色づき始め、梅雨の季節を楽しむのも束の間・・夏の訪れも同時に感じる頃となりました☀お気に入りの傘や長靴を身に付け嬉しそうに登園してくる子どもたちの姿に雨の日も楽しい発見が隠れていることを感じさせられた6月でした。どんな時もどんなことも楽しむことを忘れない子どもたちから学ぶことが日々沢山あります!!!
先日の運動会では温かい拍手をありがとうございました。運動会が終わった今でも「ディズニー体操踊りたい♪」「親子でビューン踊りたい♪」とリクエストがとまりません。頑張る姿を見てもらった嬉しい気持ちや達成感は今後に繋がる自信となったことと思います。この気持ちを大切に更に高めて育んでいきたいです。又、運動会を経験してから少しずつそれぞれが友だちにも目が向き始めています。「一緒に遊ぼう」と誘い合う声が聞こえてくるようになりました。クラスの仲間と過ごすことの居心地の良さを子どもたちなりに感じてもらえるように残りの1学期を大切に過ごしてまいります。
水遊びの準備のご協力ありがとうございます。暑い日には夏ならではの水遊びを通して体調管理に気をつけながら沢山の発見を楽しむ時間を作りたいと思います☆
- みんな大好き お砂場遊び♪
- ゲーム「ボール送り」
ちゅうりっぷ組クラスだより 2022.6.30
【7月のねらい】・保育者や友だちと一緒に水、砂、泥に触れ、遊ぶ心地よさを味わう。
【主な活動】・水遊び ・お祭りあそび
例年よりも早く梅雨が明け、暑い日が続いていますが、天気のいい日には水遊びを楽しみ、元気に過ごしています♪
先日の運動会では、沢山の拍手をありがとうございました。朝、集まったお父さん お母さん達を見て「今日本当の運動会みたいだね」と年少らしい可愛い声も♪初めての運動会で緊張も見られましたが一人ひとりが今持っている力を出せていました!
ずっと楽しみにしていた“親子でビューン”では、大好きなお家の方と沢山触れ合い、弾ける笑顔が見られました!ご協力ありがとうございました。運動会での経験が自信となり、色々な活動にも意欲的に取り組む姿が見られます。
友だちにも目が向くようになり、関わりや言葉のやり取りが増えた分、自分の思いが相手に伝わらない経験や思い通りにいかないこともあります。お互いの気持ちを聞き、受け止めながらどうしたら良いか一緒に考えています。「貸して」「いいよ」「使ってるから待ってね」とその都度、必要な言葉を伝えながら関わっています。時には子ども同士のやり取りを見守ることも大切にしています。“友だちと一緒って楽しいな”と色々な活動を通して感じられるように関わっていきたいです。水分補給を行い、体調に気を付けながら7月も元気に楽しく過ごしていきましょう。
- ☆楽しみにしていたみずあそび☆
- 水鉄砲を上手に使っています♪
- 大人気のエプロン♪
「共に生きる」を、子どもたちの姿勢から……
「あなたがたも聞いているとおり、『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたがたの天の父の子となるためである。(マタイ福音書5:43~45)」
園長 佐藤 直樹
「きずな」と言う相和私立幼稚園協会発行の機関紙がいずれ、お手元に届くと思います。今回の「きずな」の編集後記にも書きましたが、いよいよアフターコロナの時代に入ろうとする最中、ウィズコロナの姿勢こそがより一層、求められる事となるでしょう。「With=一緒に」とは、つまり「共に」生きなければならない事を指しています。ただし、誰も人に害を与えるコロナウィルスと共に生きたいと思う人などいるはずもありませんが、こればかりは自分たちの一存では如何ともし難い訳です。そこで私たちは、例え共存したくない相手であっても、それを受け容れつつ対応するところで「共に」生きる事は実現します。
子どもたちの幼稚園生活にも、自分が「やりたいこと」「好きなこと」「出来ること」もあれば、「やりたくないこと」「不得意なこと」「やらざるを得ないこと」とも「共に」生きていかなければなりません。こうした得手不得手でさえも、子どもたちは、それらを園生活のやるべきこととして「受け容れ」つつ、きちんと取り組む事によって、自分でも「やれること」「好きにもなれること」「出来ること」にしてしまうのは、まさに己に打ち克つ地道な努力とも「共に」生きようとするからなのでしょう。
コロナ禍に何度となく耳にした「克服」の二文字は、「戦う」事・「抗う」事よりも、「共に」生きていく中で、敢えて己に克つことすら求められる事とも「共に」生きていこうとする中で実現していくのかもしれません。今回のイエス・キリストの福音のことばにも、そんな響きが感じられます。
モンテッソーリだより ~「これ やってみようかな?」~ 2022.5.31
子どもはみんな、すばらしい可能性をもって生まれてきます ・・・その可能性は、適切な時期に、適切な環境を与えてあげることによって、すばらしい発達をみせてくれます。
5月から年少さんも、<ゆりの部屋>でのモンテッソーリ活動が始まりました♪新入園の子ども達には、まず『お約束』を伝えます〔室内は歩く・使った物は元に戻す・鈴がなったら止まって話を聞く〕。それから、自分でやりたいことを選びます。みんな、とっても楽しそうです♪ 年中・年長さんは、はじめにモンテッソーリ教具をみんなでやってみます。その後、それぞれ自分で選び、活動します。よく集中している姿に成長を感じます(^^♪
- 野菜切り(ねこの手で)
- ピンクタワー(大きさ)
- 色水実験「色が変わった!
- ピンクタワーと茶色の階段
- みんなで 赤い棒(長さ) 【年中】
————————————————————–
モンテッソーリ教育って?
今から約100年前、イタリアで女性として初めて医師になったマリア・モンテッソーリは「子どもは自分で伸びていく力をもっている」ことを発見し、それを援助する教育法を確立しました。
自分でやりたいことを選ぶ→ 集中してくり返す→ 満足感→ 自信がつく ・・・ この学びのサイクルが子どもの心を育てます♪ 自分で選ぶことをくり返すうちに、脳の思考回路が育っていくのです。
「自分でできた!」 という満足感や自信を得て、考える力・やりとげる力がつきます。
モンテッソーリ教育では、子どもの発達を助けるために 『教具』と呼ばれる教材を使います。
また子どもが「やりたい」と思う活動のことを『お仕事(しごと)』と呼びます。
①日常生活 ②感覚 ③言語 ④数 ⑤文化 の5つの分野があります(次号より順番に紹介します)
—————————————————————-
- 幾何立体「ピッタリのったよ
- 折り紙(よく見て考えて)
- 二項式の箱 (a+b)³
- つむ棒箱(0~9)ゴムで束ねる
- みんなで数のビーズ(1,10,100,1000)【年長】
★子どもは一人ひとり違います
ゆりの部屋では「やってみたい!」という気持ち(自主性)を大切にしています。子ども達が自分で選んだ活動を自分のペースでやりとげられるように見守っています。 子どもが自分で考えて、自分らしく行動するためには『急がないこと』と『くり返すこと』がポイントです。 これからも、「ひとりでできた!」という喜びをたくさん経験して、もっともっと笑顔になってほしいと思います。 そして、親子いっしょに成長を喜び合えますように ♡