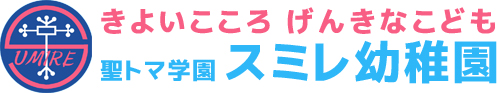幼稚園だより
ちゅうりっぷ組クラスだより 2025.12.19
今年も残り僅かになりました。街中はクリスマス一色で、鮮やかに色づいていますね。
先日のクリスマス会は緊張している様子でしたが、保護者の皆様に素敵なダンスをお届け出来たのではないでしょうか。子どもたちは、普段遊んでいる時間を練習に充てて、毎日一生懸命取り組んでいました。「お家でも練習してるよ」と教えてくれた子も♡本番だけでなく練習期間も含めて、保護者の皆様に褒めていただけることは、子どもたちの自信に繋がったはずです。
今回の経験を 通して、みんなで作り上げる良さを少し感じたのか、遊びにも変化が見られてきました。園庭でバナナ鬼やドロケイ等、ルールのある遊びをクラスや学年の垣根を越えてで楽しんでいます。一学期より更に友だち意識が強く芽生え、相手の名前を呼んで誘ったり、「順番にしよう」「じゃんけんで決めよう」とやり取りも増えてきました。自分の思いを伝えるのに一生懸命だった9月とは違い、「友だちと楽しく遊ぶため」に相手のことを互いに考えながら遊ぶ子どもたちに、大きな成長を感じます。友だちとぶつかることも多いですが、大人が解決するのではなく「子どもたち自身が」どうしたらいいのか考えることを大切に、引き続き 関わっていきたいと思います。
短い冬休みですが、体調には十分に気を付けてお過ごしください。
また、元気な姿で皆様に会えることを楽しみにしています🎵
- くりすますかい がんばりましたね♡ かっこよかったです!
つぼみ組クラスだより 2025.12.19
寒さが一段と厳しくなってきたこの頃。子ども達は北風にも負けず、元気に外遊びを楽しんでいます。入園して約3カ月、子ども達それぞれが、自分のぺ-スで大きく成長してきました。お兄さんお姉さんのやさしさに触れ、毎日笑顔で生活しています。たくさん遊び、たくさん活動に参加してきました。
お母様から離れ不安だった登園から、いつの間にか楽しみを見つけ、意欲的に取り組むたくましい姿に変わっていき、一緒に生活する中で一人ひとりの良いところをたくさん見つけることができました。いよいよ、年少組の部屋で一緒に生活が始まります。これからも刺激を受けながら、つぼみ組さんらしく成長していくことを期待しています。
今年度から新たな取り組みの「満三歳児受け入れ」のご協力ありがとうございました。予定の変更等など手探りのところがありましたが、保護者の皆様には、ご理解いただきながら子ども達を笑顔で迎え楽しく生活を送ることができましたこと、感謝しています。これからもご理解・ご協力をお願いいたします。
- 製作活動にチャレンジ!
- ほうれん草育てたよ!
イエス・キリストは 誕生する場をさがしています
園長 佐藤 直樹
「クリスマスとは何のお祝いでしょうか?」と民放ニュースで特集が組まれ、街頭質問をしていました。その答えとして「サンタクロースの何か…」「全然、考えた事ありませんでした」「キリストの………復活(残念!)」などの答えに微笑ましさを感じました。
先日おこなわれた「クリスマス会」で、年長の子どもたちが演じた『聖劇』の中に、その答えはありました。それは、全ての人の救いのために、神様が神様であるにも関わらず、私たちと同じ人となられたことを祝うのがクリスマスです。マリアとヨセフが泊まるための宿屋を探していたように、私たちの間にもイエス・キリストがお生まれになる場所をつくっていくことが求められています。
日本では本当のクリスマスがあまり認知されていないように、街中のどこを見ても、イエス・キリストの姿を見ることは出来ません。キリスト教幼稚園に通われるのを機に、イエス・キリストがお生まれになる場所(新しい年、ご家庭、皆さまの心)づくりを通して、キリストの平和に満たされた、穏やかな日々となりますように。特に、子どもたちのいる場所が、イエス様がいつも共にいる場でありますように。
貧困の現実に驚いた子どもたちとのクリスマス献金
園長 佐藤 直樹
先日、全学年に「神さまのお話し(宗教)」をした折、「クリスマス献金」の話をしました。その際、ゴミ山に鉄クズ等を拾い集めに来る子どもたちや、地面に落ちたごはんカスを拾い、それで当座の飢えを凌ごうとする子どもの写真を見せると、「えっ、こんな状況の子どもがいるの?」という驚きの表情をしていました。自分自身も数年に渡りフィリピンで生活してきた経緯もあり、ゴミ山の現実や、スラム街の貧困を、子どもたちの姿を通して目の当たりにしてきました。
その日の降園の折に、二人の子どもから「園長先生、私、お手伝いをしてクリスマス献金をするね」と言う「真心献金」の意味をしっかり汲んだ応答をもらいました。
クリスマス献金に参加する上で、あたかも現地にいる、貧困の子どもへの奉仕をするかのように、幼稚園で自分のやるべきことを自分ですることや、家庭でお父さんやお母さんのお手伝いに励むこと。また自分が貧困にある子どもたちに優しく接するかのように、幼稚園のお友だちや、家庭の 兄弟姉妹にやさしく接することなど、子どもの優しい「真心」は、思いやりのある行動や親切を通して現れます。子どもの純粋な「真心」から溢れる、やさしい行動に触れながら、ご家庭皆さんで「クリスマス献金」に参加して戴けると嬉しいです。
モンテッソーリだより ~ 数(かず)っておもしろい!~ 2025.11.28
自分の年齢が数えられるようになった頃から興味をもつ「数」の世界。「数」は子ども達の日常生活に密着しています。 例えば、出席シールをきれいにはる・服をたたむ・使ったものを元に戻す・紙をぬう・編むなど、一つひとつを正確にやってみようとする心(秩序感)が数の土台をつくります。また、感覚教具(ピンクタワーや赤い棒など)を十分に使い、感覚の違いがよくわかるようになることが大切です。【感覚の敏感期】
数教育は、五感を使って具体物を数えたり分けたりすることから始め、徐々に数字に置きかえていきます。
- ぬいさし「ひとりでできるよ♪」
- のりで貼る「ピッタリはれたよ♪」
- ピンクタワー「これは大きいかな?小さいかな?」 (目を閉じて手渡された立方体をよく触る→並べる)
- ピンクタワ-「ダイヤモンドみたいに♪」
- 3本あみ「クリスマスみたい♪」
★ご家庭でできること ~ 遊びやお手伝いを通して★
「どんぐりを数えてみよう」「コップを5こ並べて」「クッキーを3こずつ分けて」など、具体物を使って、「数」に親しむチャンスがあるといいですね♡ また、折り紙は集中力や想像力、数学的思考力が身につきます。
- 数遊び(0~9)数を記憶し物を使って正確に把握する
- 鉄製はめこみ(連続模様)「きれいに♪」
- 連続数字「面白くなってきた」
- はたおり「いろんな色を使ってみる♪」
- はたおり「次はどの色にしようかな♪」
————-モンテッソーリ教育の数教具———————–
・教具を手でさわり、数え、確かめることによって、理解を深めるように工夫されています
⇒数量(具体物)・数詞(数えること)・数字の3つが一致した時、その数を理解したといえます
・感覚教具で行った活動(同じものを探すこと・順序づけ・分類)が数教育のベースになります
・数の土台は生活の中にあります → 秩序のあるものは、すべて数につながっています
教具 — 砂数字板、赤と青の数棒(1~10)、つむ棒箱(0~9)、数あそび、セガン板Ⅰ・Ⅱ(数の構成)、
数字うつし書き、10進法(1,10,100,1000)、100並べ(1~100)、連続数字(順番に数を書く)など
- 赤と青の数棒(1~10)
———————————————————
★年長さんには、重さが実感できる数のビーズを使って、1から1000の数を紹介します 【10進法】
先入観をもつ前に、数に出会った子どもは、大きい数への恐れをもちません。
「1のビーズはとても小さい」 → 10 → 100 →「1000は大きくて重い」・・・手に持つことによって数の違いを体感できます。どの位も10個集まると次の位の1個と同じになります。
どんな時も、『感じる』こと(感覚)が大切です♪