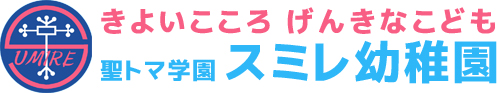幼稚園だより
ちゅうりっぷ組クラスだより 2021.1.29
【2月のねらい】・生活に見通しを持ち、自分で出来ることに進んで取り組む。・自分の思いを言葉で伝え、友だちの気持ちにも気付く。
【主な活動】・はじき絵 ・おひなさま製作 ・おかしやさんごっこ準備
子どもたちの元気な挨拶とともに新しい年が始まりました!寒い日が続きますが「外で遊ぼう!」と声を掛けると「イェ~イ!!」と大歓声!!外では鬼ごっこや影踏み、中当て等、少しずつみんなでルールのある遊びを楽しんでいます♪室内でもカードゲームやバランスゲームが流行っていて、友だちにルールを教えてあげる姿があります。でもゲームは勝ち負けがあるので、真剣!!負けず嫌いな一面が見られたり、上手な友だちを見て「お~すごい!」「次は頑張ろう!」とお互い意識しあいながら、友だちとの関わりを深めているのを感じます。「~ちゃんと一緒に遊びたい!」という気持ちも強くなってきているのと同時に、なかなか輪に入れずに困っていたり、「どう言えばいいか分からない…」と言った声も聞こえてくるようになりました。「どんな風に言えば友だちに伝わるのかな?」と一緒に考えることで、少しずつ勇気を出して自分の言葉で気持ちを伝える姿が見られ始め、日々の関わりの中で色々なことを学んでいるようです☆
1月の製作は、はさみで〇や△を切ったり、クレヨンだけではなくペンや絵の具など様々な教材に触れる経験を作ってきました!自由遊びでも切り紙をしたり、細かい塗り絵を集中して塗ったりと手先を動かすことが上手になってきています。まだまだお家で過ごす時間が多いと思うので、
一緒に折り紙やはさみで簡単な形を切ってみたりとお家時間を楽しめるといいですね♪2月もみんなで出来る感染予防をしっかり行い、年中に向けて心の準備をしながら、元気に楽しく過ごしていきたいです(^^)!何か心配なこと等ありましたら、いつでも声を掛けてください☆
~3学期も宜しくお願い致します!~
- 先生の手作り エプロン❤ 「かわいい~❤」とお気に入りです♪
- こま作り
- 鬼のお面製作☆「デカルコマニー」という技法を楽しみました!
マタイによる福音書22:35-40 律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか?」イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。」
今、もう一度、「自己愛」……正しく自分を愛してみませんか?
園長 佐藤 直樹
『神と人を愛する』こと‼それが一番大事とイエスは語ります。そして、あなたのすぐ傍に見えているその人を愛することが、見えない神をも愛することにもなるようです。そして、イエスは隣人を愛する上で『自分のように』愛することを求めておられます。
二回目の緊急事態宣言が発令された最初の週末の渋谷センター街で、街頭インタビューを受けた複数の若者たちの口から出た言葉が「自分がコロナに罹ったら、罹ったらで仕方ないと思って、ここに出て来ています」でした。個人的に、この言葉に哀しみを感じたのは、利己的な発想でしかないかのような物言いよりも、自分のことを自分自身が愛せていないこと…自分のことを自分自身で大切に思えていないがゆえの「自分がコロナに罹ってもいい」と言う価値観がショックでした。他者に感染を広げない…医療崩壊を起こさないような配慮に取り組む事に意識が向かないのではなく、自分が感染しても構わないから、目先の自分の欲求を満たしたい!と言う刹那的な思いが優先され、己自身が愛し愛される事そのものより勝ってしまっているメンタリティーが都市部の人出を減らせない要因にも繋がっていないでしょうか?
それだけに「自分は大切な存在なのだ!」と己で己を愛することが出来る“自己愛”の内に、イエスの語る『隣人を自分のように愛する』隣人愛や他者の命への尊重と配慮は実現するのでしょう。「自己愛」に満ちた、自分も含めみんなが大切にされていく世の中となるのか?はたまた「利己愛」による、自分の欲するままに行動することで、自分だけでなく、みんなを不幸に繋げる世の中となるのか?コロナ禍の今こそ「隣人愛」の行動と実践がモノを言います!
モンテッソーリだより ~平和をつくるための教育~ 2021.1.29
子どもには、一つのことに夢中になり、同じことをくり返しながら、能力を伸ばす時期があります。
モンテッソーリ教育では、それを『敏(びん)感(かん)期(き)』と呼んでいます。 敏感期には、言葉・秩序・小さなもの・感覚・文字・数・文化など様々なものがあります。 わが子が「今、何の敏感期なのか」をよく観察し、やりたいことを十分にくり返しできる環境を整えてあげることが、子育てのカギです♪
子どもは、求めているものにぴったり合うものに出会うと、何回でもくり返します。 そして、手と五感を使ってくり返すたびに、より集中し、やり終えた後は満足感を得て、顔が変わっていくのがわかります(^^♪
- 野菜切り ・ 色水実験
- ぬいさし(和ばさみも使えます)
- 2本あみでおばけ👻
- 幾何立体「ぴったり!」
- 赤と青の数棒(手を使って数える)
- 折り紙「小さい折紙でも作れる!」
- 十進法「3000!重い!」
- 連続数・・よく考えて、ゆっくり、ていねいに
- 織る紙【年長】 色を選んで、専用の棒に挟んで…集中!
——モンテッソーリの文化教育(コスミック教育)——————————————
◆モンテッソーリは 『世界には平和をつくるための教育が必要』とし、コスミック教育を確立しました。 宇宙に存在する様々なこと(生物・歴史・地理・宗教・音楽など)を伝えていこうとする壮大なスケールの領域です。年長児向(6才から文化の敏感期)
◆地球のすべてのものはつながっていて無駄なものはない→一人ひとりが大切
◆知識を与えることが目的ではなく、「どうして?」という気持ちを大切に、観察したり、手でさわるなどの体験を通して、自分でその先を考えていきます。
◆全体から部分へ進めていきます。(宇宙からスタートします→地球→陸→国…)
- 年長さんに『宇宙・地球』の話をしました。聞く力・考える力・考えたことを言葉にする表現力に驚きました!(地球儀・世界地図などを使います)
———————————————————————————————–
★「待つ」
子どもは自分がやりたいこと・選んだことを尊重され、「できた!」の体験を積み重ねるほど自信がつき、「大切にされている」という自己肯定感を育みます。なるべく指示せずに、子どもが自分で考えて行動できるチャンスをたくさんつくってあげましょう。 あせらせず、子どもの力を信じて 「待つ」ことが大切です♡
でも時には、「次は何をしたらいいかな?」と声をかけて、サポートしてあげるといいですね。
1月26日、29日 第16回プレイルーム
今回の活動は「鬼のお面製作」でした。節分のお話をきき、はさみとのりを使って取り組みました。
いつもはお家の人に手伝ってもらっていましたが、今回は自分でできることは自分でやるように声掛けをしたので、「自分でやる!」と頑張っている姿がありました。先生が助っ人になり、お家の人の手を借りずに完成させることができました。前回より今回!と回を重ねるごとに成長を見せてくれる子ども達です。鬼のお面は節分の豆まきの時に使ってね!とっても上手にできました。
1月19日、22日 第15回プレイルーム
今回は太鼓・タンバリン・鈴・カスタネット・木琴・鉄琴・マラカス・トライアングルの楽器を使って音を楽しみました。自分のやりたい楽器を選んで「おもちゃのチャチャチャ」の曲に合わせて合奏をしました。ピアノに合わせて楽器から出る音をそれぞれ楽しんでいる様子がありました。ニコニコ笑顔がいっぱいでした。